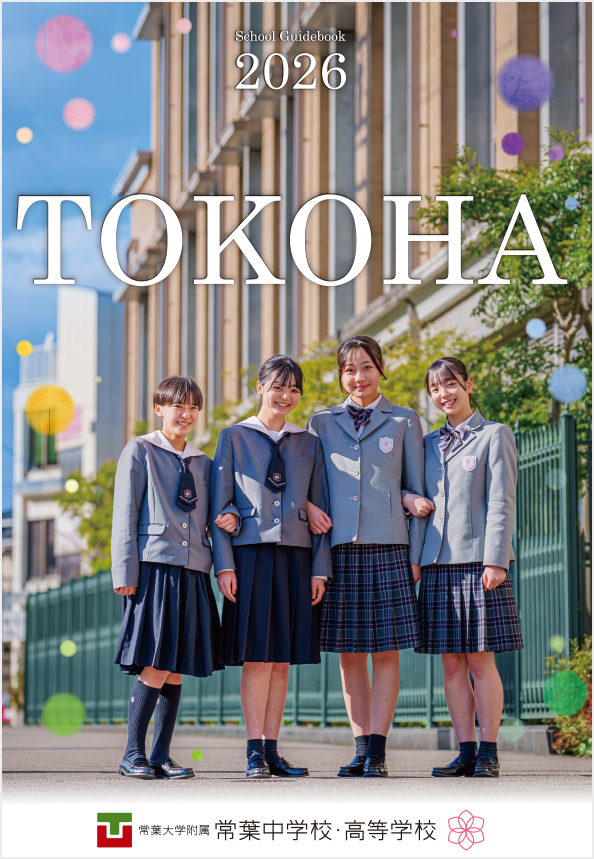校誌「とこは」NO.72 投稿
「今日は、1月14日、愛と希望と勇気の日♪」
朝、車のエンジンをかけてしばらくすると、カーナビから「今日は何の日」という音声が流れます。今朝の「愛と希望と勇気の日」という言葉が刺さり、調べてみることにしました。
1959(昭和34)年のこの日、南極観測船「宗谷」が昭和基地に着き、前年に置き去りにした15頭の 樺太犬のうち、タロとジロが生きていたのを発見。生きることへの希望と愛することを忘れない ために制定。
昔、高倉健主演の映画、『南極物語』で、悪天候に阻まれやむなく南極に置き去りにされた樺太犬タロとジロが、極寒の地で生き抜く姿を描いた奇跡と感動の物語の映画を観たことを思い出しました。YouTubeで検索すると、画像が粗い当時の映画を観ることができました。2011年、TBS開局60周年記念番組として、木村拓哉主演の日曜劇場『南極大陸』を放送していました。
この「南極観測」は、戦後10年の日本が初めて一つになったと言われている一大プロジェクトでした。昭和30年代は、東京オリンピック開催や新幹線開通など、敗戦から人々はただがむしゃらに働いて、生活や経済を立て直していた時代でした。そんな中、世界で未知の大陸「南極」の観測が計画されます。アジア諸国で唯一参加を表明した日本は、「敗戦国」として何ができるんだと世界から罵倒されていました。しかも日本に割り当てられた観測場所は、氷点下50度、風速100メートルのブリザードが吹き荒れる最悪の場所でした。国も支援に後ろ向きだった中、「南極に行って欲しい」と願う子どもたちが、自分たちのおこずかいを募金する活動が全国へと広がり、結果国や企業を動かすことになりました。決してあきらめることなく、南極大陸を目指した当時の日本人たちや、生き延びた樺太犬のタロとジロの感動が、今の日本に足りないものを教えてくれます。
戦後、整備されてきた水道や橋や高速道路などのインフラや日本中に植えられた、ソメイヨシノの桜も、50年以上が経過して、いろいろなところで歪みが生じています。昨年の元日に起こった能登半島地震の復興はほど遠く、過疎地の復興はあとまわしといった感じです。これまで、当たり前にできていたことが、そうではなくなっていることを痛感します。周囲の暮らしを見ると、空き家がいっぱいです。道路標識も消えかけていてもそのままです。こども食堂を頼りに生活をしている家庭も増えています。経済状況の指標となる、GDP(国民総生産)は、2024年の世界ランキングでは、これまでの3位から4位に転落し、5位のインドにも抜かれそうな状況です。
「校長先生、未来を生きる私たちに、そんな暗いメッセージは勘弁してください。」という声が聞こえてきます。しかし、今の日本はこれが現実なのです。戦後の日本とは違い、今の私たちの生活はとても豊かになったけれど、南極観測が始まったころと比べると、必死に生きるとか、よりよいものをみんなで創っていこうという気持ちが足りないような気がします。みなさんには、世の中のできごとにもっと関心をもって、何でだろう、自分には何ができるのだろう、と意識を高めて欲しいのです。これからの未来を築くみなさんは、今の大人たちよりずっと柔軟な思考を持ち、デジタルを駆使する能力に優れ、他者を思いやる優しい心にあふれているのですから、自分たちにもっと期待してください。
日本の南極観測は、60年以上たった今も続いているそうです。気象、天体、地球科学、生物学の観測が目的だそうです。今年も第66次南極観測隊が、南極観測船「しらせ」に乗船し、昭和基地へと向かったそうです。