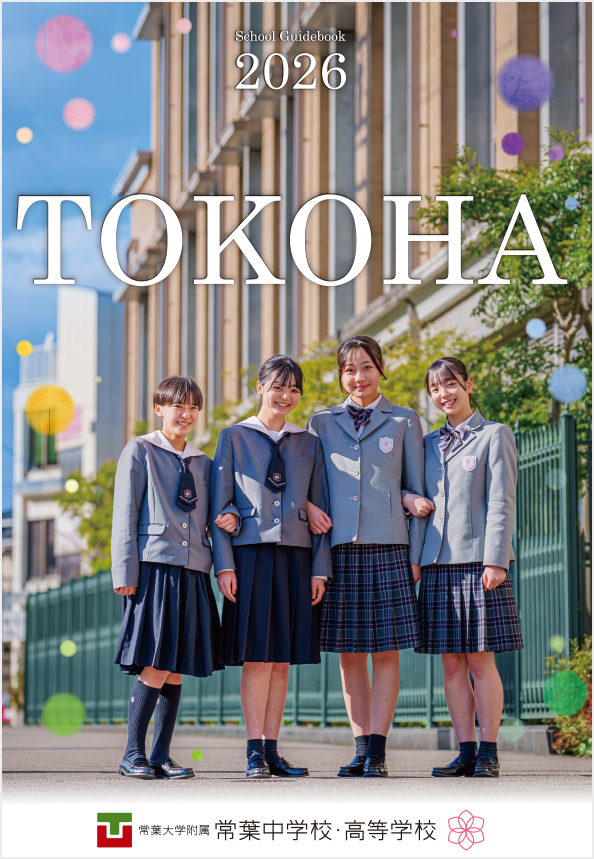3月3日桃の節句に、第75回卒業証書授与式を挙行しました。101名の卒業生が巣だっていきました。あいにくの雨模様ではありましたが、別れ涙の雨でした。それぞれの道で元気に活躍されることを願っています。
校長式辞より
冬の寒さも和らぎ始め、吹く風にも春の気配が感じられる今日この佳き日に、ご来賓、保護者の皆様のご出席を賜り、第75回卒業証書授与式を、盛大に執り行うことができますことを心より感謝申し上げます。本日、高等学校の全課程修了を認められました101名の生徒のみなさん、御卒業おめでとうございます。そして、今日までお子様の成長を見守り、励まし、支えてこられた保護者の皆様、ご家族の皆様にも心よりお祝いを申し上げます。
皆さんの胸元にあるコサージュは、母の会の皆様の手作りです。母の会は、学校生活を送るみなさんを陰ながら支えてくださいました。来年度からは、PTAの活動に引き継がれることになります。私たちの校舎の向かいには、駿府城の石垣があり、市民文化会館が立っていますが、母の会ができた、70年前は、静岡刑務所がありました。昔の校舎は3階建てでしたが、屋上からは、富士山がきれいに見えました。同時に、刑務所の中もよく見えてしまったそうです。そこで、母の会のみなさんが、桜の木を植えれば、学校から刑務所を見ることもないし、刑務所にいる囚人も心がなごむだろうと、たくさんの桜の木を植えたそうです。お堀沿いの桜は、常葉の母の会が植えてくれたことが始まりでした。
あとひと月もすると、駿府城の石垣に植わっているソメイヨシノが、水面(みなも)に垂れ下がる光景に、暖かな春の訪れを感じます。「なぜ春になると、桜の花は咲くのでしょうか」「暖かくなるから」間違いではないですが、桜にはすてきなストーリーがあります。
桜は、春に花が散ったあと、青々とした若葉が幹を覆います。夏の暑さに耐えて、秋になると黄色に葉が色づき、日が短くなる頃に、葉が落ちます。その時には「花芽(はなめ)」という、雨風に負けないように、堅い葉で守られた小さな芽が生まれます。寒くなると、「越冬芽(えっとうが)」という芽に包まれて、成長を止めて「ひと休み」します。やがて、春の気配を感じて、つぼみがふくらんできます。この様子を桜守(さくらもり)の佐野藤右衛門(さのとうえもん)さんは、「笑いかけ」と言っています。桜は、満開に咲くときばかりに目がとまりますが、それまでの過程には、たくさんの物語があります。
卒業生の皆さんも、この常葉で過ごした3年間は、楽しいことや良いことばかりでなく、つらかったこと、悩んだこともたくさんあったと思います。桜の花のように、夏の暑さに耐えて、時には冬の寒さに休み、越冬芽のように、誰かに助けてもらい、今日、笑顔の卒業式を迎えることができました。皆さんは、桜の花のように、咲くべき時が来たから咲く花です。
しかし、これからの長い人生において、大きな選択を迫られる場面がいく度もあることでしょう。選択の基準は、人それぞれですが、選択に困ったときの基準を3つお話します。まず、「無難な道より、自分が面白くわくわくする道」を選んで、チャレンジし続けて欲しいと思います。わくわくする道がいつも楽な道とは限りません。新しいことに挑戦するには、不安がつきものです。しかし、そのドキドキや緊張感こそが、みなさんの人生を豊かにしてくれます。2つ目は、「楽な方より、あえて困難な道」を選んでみてください。なぜなら、その先には、必ず「成長」と「新しい景色」が待っています。最後に、選択肢が多すぎて、どうしても決められないときには、「自分が本当に大切にしたいものは何か」を考えてみてください。選択に困ったときには、一度立ち止まり、「未来の自分がどう思うか」「本質をとらえて行動できるか」考えてみてください。
Make new mistakes! 新しい失敗をしよう!と、皆さんに呼びかけました。これからの人生においても、失敗を恐れずに、まずやってみようという勇気をもって行動にうつしてください。喜びは行動とともにやってくるはずです。
結びに、3年間あるいは6年間、保護者の皆様からお寄せいただきました、本校の教育活動への温かなご支援・ご協力に、厚く感謝を申し上げます。 卒業生の皆さん、これから歩むそれぞれの道を、目標に向かって一歩ずつ、周囲とよい人間関係を築きながら前進してください。これからの未来が皆さんにとって輝かしいものであることを心よりお祈りし、式辞といたします。
令和7年3月3日
常葉大学附属常葉高等学校 校長 木宮 暁子